
早稲田大学人間科学部の世界史で8割取る対策&勉強法
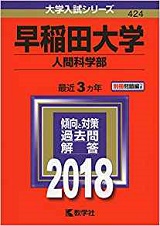
早稲田大学人間科学部の世界史の傾向と難易度
問題構成
問題構成については、本年は大問が5題、小問が49題で昨年と同じでした。
大問数は2011年度から5題で安定しています。
小問数は2015年度が47題でしたので、ここ数年安定しています。
試験時間は60分ですから、単純計算すると1問あたり1分強で解くことになります。
問題形式
問題形式は次の通りです。
空欄補充問題が23題で昨年と同じ。
正誤問題が23題で昨年が20題でしたので、やや増加しました。
本年は出題がありませんでしたが、年代整序問題は頻出です。
たとえば、2016年度大問4設問Y「モンゴル帝国の歴史の展開」です。
逆に2016年度は出題のなかった地図問題が、2017年度は復活しました。
出題される地域
出題される地域は、欧米とアジア諸地域です。
アジアでは中国史が1題必出です。
その他のアジアでは東南アジア・西アジア・日本などから広く出題されています。
たとえば、2017年度大問4はアフガニスタンという馴染みの薄い地域からの出題でした。
欧米については、ここ数年は西欧からの出題です。
時代については、古代から現代まで幅広く出題されます。
2014年度大問4「東南アジア」・大問5「アジア・ヨーロッパ」のように現代史が2問出題されることがあります。
逆に古い方では先史が出題されることもあります。
たとえば、2017年度に大問3設問X-A「ラスコー」が出題されました。
出題分野
分野別では、文化史が頻出です。
たとえば、2015年度大問1「暦と地図」・2「儒教・仏教と政治・文化」のように2題が大問のテーマとなることもあります。
難易度
難易度としては、正誤問題でやや詳細な出題があります。
たとえば、2017年度大問1Y-⑤「ジャーヒリーヤ」を問う問題がそうです。
とは言え、全体としては教科書レベルの設問が多いです。
早稲田大学人間科学部の世界史の対策&勉強法
対策&勉強法①文化史をおさえておこう
上記のように、文化史は頻出です。
たとえば2017年度大問4設問Y-④「玄奘」についての問題がそうです。
2017年度は出題されませんでしたが、図版が用いられることもあります。
たとえば、2016年度大問4設問Y-⑤「パスパ文字」を問う問題がそうです。
教科書や資料集の写真には、目を通しておきましょう。
文化史はどうしても手薄になりがちです。
事項を時代と地域、分野ごとに表にまとめておくと効果的です。
さらに、宗教史も整理しておきましょう。
学部の特徴で、2017年度大問1「イスラーム史」がそうであったように、まるまる大問一つがそれに充てられることもあります。
対策&勉強法②正誤問題と選択問題は基本をおさえよう
これも上述のように、正誤問題でやや細かな問題が出題されることがあります。
たとえば、2017年度大問3設問Y-⑥「ヴァンデー反乱」の起こった年を問う問題がそうです。
選択問題でも詳細な設問が出題されることがあります。
2017年度大問2設問X(1)「薊」がそうです。
とは言え、教科書レベルの問題が大半なのですから、基礎知識をきちんと身につけるようにしましょう。
ケアレスミスをしないように、よく練習しておきましょう。
またやや詳細でも、消去法で解答できるものもあります。
たとえば2017年度大問1設問X「ハワーリジュ」がそうです。
消去法は時間がかかりますが、確実です。
対策&勉強法③年代整序をおさえておこう
2017年度は出題がありませんでしたが、上記のように2016年度は出題されましたし、2015年度大問3設問Y-⑤でも出題されています。
いつ復活してもおかしくないので、問題集などで練習しておきましょう。
その際、一つの地域の通史だけではなく同時代史の練習もしておきましょう。
対策&勉強法④日ごろから図版や地図を見るようにしよう
上述のように、地図問題が復活しました。
2017年度大問4設問Y-③中央アジアの国名を問う問題がそうです。
現在の主な国名と位置とを地図帳などで確認しておきましょう。
対策&勉強法⑤中国史は周辺地域もおさえておこう
中国国内だけではなく、周辺民族との関係が出題されることがあります。
たとえば、2017年度大問2設問Y-③「土木の変」がそうです。
中国の王朝と周辺地域の関係は、表や模式図でまとめておくと効果的です。
対策&勉強法⑥現代史をおさえておこう
2016年度・ 2017年度と連続して出題されましたので、現代史は要注意です。
時事問題の要素を持つ問題も出題されます。
たとえば、2017年度大問5「ヨーロッパ統合」がそうです。
これはイギリスのEU離脱を受けたものでしょう。
ニュースや新聞にも目を通しておく必要があります。
対策&勉強法⑦苦手分野をつくらないようにしよう
繰り返しになりますが、時代・地域・分野ともに幅広く出題される傾向にありますので、抜けのない学習を心がけてください。
とくに文化史や現代史は後回しになりがちです。
計画的に学習し、通史は早めに終わらせるようにしましょう。
対策&勉強法⑧過去問は必須
人間科学学部はもちろんのこと他学部の過去問もできる限り解くようにすると良いでしょう。
直前の対策として、文学部以前に試験が実施された学部の問題を入手して解くことも有効です。
似たような問題が出題されることがあります。
本年では人間科学部の試験日が2/18ですから、文化構想学部(2/12)と国際教養学部(2/13)、法学部(2/15)、文学部(2/17)の問題を解くことが可能です。
⇒1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら
⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら
⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら
現役の時に偏差値40ほど、日東駒専に全落ちした私。
しかし浪人して1ヶ月で「英語長文」を徹底的に攻略して、英語の偏差値が70を越え、早稲田大学に合格できました!

私の英語長文の読み方をぜひ「マネ」してみてください!
・1ヶ月で一気に英語の偏差値を伸ばしてみたい
・英語長文をスラスラ読めるようになりたい
・無料で勉強法を教わりたい
こんな思いがある人は、下のラインアカウントを追加してください!
筆者は現役時代、偏差値40ほどで日東駒専を含む12回の受験、全てに不合格。
原因は「英語長文が全く読めなかったこと」で、英語の大部分を失点してしまったから。
浪人をして英語長文の読み方を研究すると、1ヶ月で偏差値は70を超え、最終的に早稲田大学に合格。
「1ヶ月で英語長文がスラスラ読める方法」を指導中。
⇒【秘密のワザ】1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた方法はこちら
⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら
⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら











