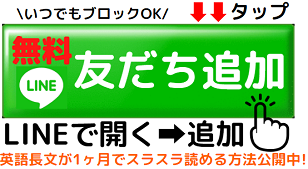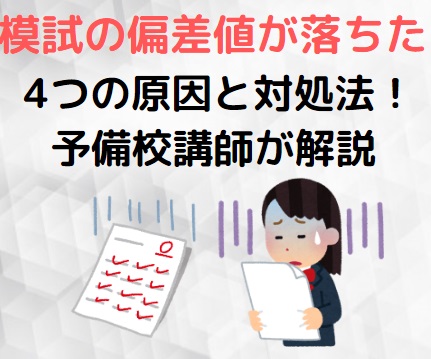
>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら
模試の自己採点をしたけれど、前回より点数が下がってしまった。
模試の結果が返ってきたけれど、偏差値や判定が落ちてしまっている。
私も受験生の時は、模試の成績が悪くて落ち込んだことがありました。
そんな時に原因をしっかりと分析して、対策したことにより偏差値は伸びていき、早稲田大学に合格できました。
これまでたくさんの受験生から相談を受けてきて、「模試の偏差値が落ちた」原因は大きく4つに分類できることが分かりました。
ここでは「模試の成績が落ちる4つの原因と対策法」を詳しくお伝えしていきます!
記事と筆者の信頼性
・筆者は模試の成績優秀者に掲載され、早稲田大学に合格
・偏差値40台から70を超えるまで伸ばし、A判定を獲得
・予備校講師として、2,000人以上の受験生を指導
>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら
目次
私の英語の偏差値が1ヶ月で40から70まで伸びた話
私は現役の受験生の時、偏差値は40ほどで、日東駒専を含む12回の受験全てに失敗してしまいました。
その原因は配点が最も高い英語長文を、全く攻略できずに、大きく失点してしまったこと。
英語長文を攻略できない限り、どこの大学の英語でも高得点が取れず、受験に失敗してしまうんです。
浪人をして最初の1ヶ月間、「英語長文の読み方」を徹底的に研究して、英語長文がスラスラ読めるようになり、偏差値も70を超えるようになり、早稲田大学に合格できました。
私が実践した「英語長文の読み方」をマネして、短期間で一気に英語の偏差値を伸ばしてみたい人は、下のラインアカウントを追加してください!
模試の偏差値/成績が落ちる4つの原因

受験勉強は誰もが努力をして成績を伸ばそうとしていますから、その中で成績が落ちてしまうこともあるでしょう。
そういった相談はたくさんいただいているので、珍しいことではありません。
その相談のデータをもとに、模試の成績が落ちてしまう4つの原因をお伝えしていきます。
4つの原因
・苦手な分野がある
・自分以外の受験生が伸びた
・模試の難易度についていけなくなった
・緊張してしまって実力が出ない
>>1ヶ月で早稲田慶應・難関国公立の英語長文がスラスラ読めるようになる方法はこちら
原因①苦手な分野がある
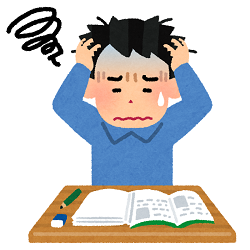
これまでは運良く、自分がニガテな部分の失点を抑えられて、成績が良かった場合。
ニガテな部分が多く出題されたとき、成績は大きく下がります。
これは運が悪かったのではなく、バランス良く実力が伸ばせていない証拠です。
例えば私が受験生の頃は、古文にニガテ意識がありました。
しかし勘や消去法で何とか乗り切れることも多く、「意外と大丈夫そうだ!」と過信してしまいました。
少し難しい問題になり、勘で答えたものがすべて外れてしまい、正解できたのは1問のみ。
「うろ覚えの知識」や「なんとなくの理解」では、大崩れする可能性があるんです。
>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら
基礎固めが本当に大切です
古文にはもともと自信がありませんでしたから、「これが実力だ」と受け入れて、基礎から徹底的に復習しました。
単語は絶対にうろ覚えが無いよう、古文文法は活用表を完璧に暗記しました。
そうすると勘に頼って答えていた古文が、「絶対にこれが正解!」と確信を持って答えられる問題がどんどん増えていきます。
模試の偏差値が大きく伸びたことはもちろん、最も難しい古文が出題されると言われている早稲田大学教育学部の古文でも、満点を獲得して合格。
自分がニガテだと感じている部分は、基礎さえ固めてしまえば、意外と難しくないものなんです。
基礎が出来ていないと問題を解いたときに、「全く解けない、自分はこれがニガテだ」と拒否反応を起こしてしまいます。
ニガテな教科・分野から逃げずに、基礎を徹底的に固めて、本番でも大崩れしない実力を鍛えましょう。
>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら
原因②自分以外の受験生が伸びた

模試の偏差値や判定は「相対評価」で、受験生の中での現時点の自分のランクを表します。
自分の実力が伸びたとしても、それ以上に他の受験生が伸びていれば、成績は落ちてしまいます。
特に受験の序盤は部活動をやっている人や、まだ本腰を入れていない人が多く、成績が高く出やすいです。
夏、秋、冬と周りの受験生もどんどん力を伸ばしていきますから、自分の実力が大きく伸びていかないと、なかなか成績の向上は見られません。
ですから浪人生の人はスタートが最高で、そこから徐々に成績が落ちてしまうというケースが良くあります。
>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら
誰よりも勉強する気持ちで取り組む

周りの受験生を大きく追い抜いていかないと、成績は伸びないということは、勉強量を増やすしか策はありません。
「勉強は質が大切」などと言いますが、「質と量の両立」ができるようでないと、成績は大きく伸びていきません。
根拠を持った正しい勉強法を実践することはもちろんのこと、「誰よりも勉強したと胸を張って言えるくらい」本気で勉強をしてみてください。
原因③模試の難易度に対応できなくなった
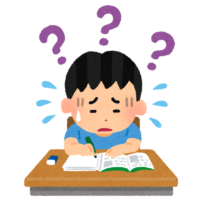
大学受験の模試は基本的に、受験が近づくにつれて難易度が上がっていきます。
春は基礎の部分が中心になっていきますが、徐々に応用的な内容も出題されるようになります。
つまり自分の力が伸びていないと、どこかで模試の難易度についていけなくなってしまうんです。
ここを乗り越えて秋以降の模試で良い偏差値を取れるようにならないと、なかなか志望校には合格できません。
>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら
実践的な問題をたくさん解こう

難しい問題を解けるようにするためには、とにかく基礎を固めたうえで、たくさん問題を解くこと。
問題を解くことで「発想力」や「対応力」が磨かれていき、難しい問題へのニガテ意識が薄れていきます。
ここから徐々にステップアップしていき、志望校のレベルの問題まで解けるようにしましょう。
忘れてはいけないのは「難しい問題を解く前に、基礎を固める」こと。
私も受験生の時は応用問題を早く解けるようになりたくて、難しい参考書や問題集、過去問に手を出していました。
しかし基礎が固まっていない状態で応用問題を解いても、いつまで経っても成長は見えてきません。
まずは基礎を固めて、その土台をもとにアウトプットしていくからこそ、実力が伸びていくんです。
原因④緊張でミスを連発してしまう

模試で緊張してしまって、本来の実力を出せないという人もとても多いです。
ケアレスミスを連発してしまったり、時間配分をミスしてしまったり。
点数を大幅に落としてしまうこともあるので、緊張は最大の敵になります。
入試本番の緊張は、合否に直接の影響を与えてしまいますので、対処していきましょう。
>>偏差値が1ヵ月で40から70に!私が実践した「たった1つのワザ」はこちら
自信をつけることが一番の薬

私も偏差値が低かった時は、悪い意味での緊張がとても大きかったです。
「偏差値が低かったらどうしよう」、「全然解けなかったらどうしよう」、「友達にバカにされたくない」などなど。
一方で基礎をガッチリと固めて、問題演習も繰り返してからは「やるべきことをやったから、解ける問題がたくさんあるだろう」と論理的に自信がつくようになりました。
根拠を持った勉強を進めたうえで、良い偏差値が取れるようになると、どんどん自信もついていき、緊張もしなくなっていきます。
悪い緊張をする原因は「自分の学力に自信が無いから」、「問題の演習量が足りていないから」です。
逆に言えばしっかりと勉強をしていれば、少しくらい緊張したとしても、偏差値は伸びていきます。
受験は勉強した内容を問うテストですから、緊張したからと言って、大幅にパフォーマンスが落ちるとは考えにくいですからね。
メンタル面が大きく影響を与える、スポーツなどとは性質が大きく異なります。
良く「緊張して実力が発揮できませんでした」という相談が届きますが、少し厳しいことを言うと「緊張を言い訳にしてしまっている」可能性があります。
「実力はあるけど、緊張で発揮できなかった」のではなく、「実力が足りずに自信が持てないから、緊張してしまった」と考えるようにしてください。
そうでないと前へ進んでいけませんし、いつまでも成績は伸びていきません。
>>1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら
模試の偏差値が落ちた原因と対策まとめ
模試の偏差値が落ちた時は苦しいですし、「勉強したことが無駄になった」ような気がしてしまいますよね。
しかし一度勉強した内容は、勉強しなおしたときにとても効率良くインプットすることができます。
成績が伸び続ける人の方が少ないですし、誰しもが何らかの辛さを感じながら進んでいくのが「大学受験」です。
困難にぶつかった時に、諦めずに対処法を考えて乗り越えるという力は、これからの人生でも大きく役立ちます。
成績が落ちてしまっても、まだまだ逆転できるチャンスは残されているので、頑張っていきましょう!
⇒1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた「秘密のワザ」はこちら
⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら
⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら
現役の時に偏差値40ほど、日東駒専に全落ちした私。
しかし浪人して1ヶ月で「英語長文」を徹底的に攻略して、英語の偏差値が70を越え、早稲田大学に合格できました!

私の英語長文の読み方をぜひ「マネ」してみてください!
・1ヶ月で一気に英語の偏差値を伸ばしてみたい
・英語長文をスラスラ読めるようになりたい
・無料で勉強法を教わりたい
こんな思いがある人は、下のラインアカウントを追加してください!
筆者は現役時代、偏差値40ほどで日東駒専を含む12回の受験、全てに不合格。
原因は「英語長文が全く読めなかったこと」で、英語の大部分を失点してしまったから。
浪人をして英語長文の読み方を研究すると、1ヶ月で偏差値は70を超え、最終的に早稲田大学に合格。
「1ヶ月で英語長文がスラスラ読める方法」を指導中。
⇒【秘密のワザ】1ヵ月で英語の偏差値が40から70に伸びた方法はこちら
⇒【1カ月で】早慶・国公立の英語長文がスラスラ読める勉強法はこちら
⇒【速読】英語長文を読むスピードを速く、試験時間を5分余らせる方法はこちら